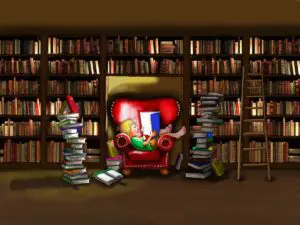本サイトはプロモーションが含まれています。
住宅火災の意味と出火原因~家庭内にひそむリスクを知ろう~
急に寒さが厳しくなり、あわてて冬物コートや暖房器具を準備した方も多いのではないでしょうか?
寒波襲来を伝えるニュースとともに増えたと感じるのが「住宅火災」の報道です。
ニュースでは住宅火災と報じられますが、一般的には「火事」のほうが身近な言葉でしょう。
そこで今回は「住宅火災の意味」と「その出火原因」そして「家庭にひそむ住宅火災のリスク」についてお伝えします。
空気が乾燥するこの時期、火はあっという間に燃え広がってしまいます。住宅火災をもたらすリスクを知り、火災予防の行動へつなげていきましょう。
住宅火災とは
建物火災の1つ
総務省消防庁の統計では、火災を「建物火災、林野火災、車両火災、船舶火災、航空機火災、その他の火災」に区分しています。
そして「住宅火災」とは建物火災のひとつであり、具体的には「一般住宅・併用住宅・共同住宅」を意味しています。
【参考文献】消防庁|令和4年(1月~12月)における火災の概要(概数)について(令和5年5月16日)/7頁
火事は住宅にかぎらない
一方で「火事」の意味は『建物、山林、船などが焼けること※』となっています。※goo辞書|火事より引用
つまり、火事は住宅に限らずあらゆるものが焼けることと言えるでしょう。
そして「火災」については消防庁が細かく規定しているのですがここでは省略し、本記事では一般的な意味である『火による災難※』として用いていきます。※weblio|火災より引用
住宅火災の出火原因
それでは、総務省消防庁の資料をもとに、令和4年における「住宅火災の出火原因」をみてみましょう。
【参考文献】消防庁|令和4年(1月~12月)における火災の概要(概数)について(令和5年5月16日)/5頁~
令和4年の件数|建物火災の約55%が住宅火災
まず「建物火災」の出火件数は『20,185件』であり、火災全体の『55.5%』で最多となっています。
このうち「住宅火災」をみてみると『11,017件』、建物火災全体の『54.6%』と半数以上を占めているのです。
そして、住宅火災のなかでは「一般住宅」が『35.6%』であり「共同住宅(17.1%)」よりも多くなっています。
※データ出典元:上記【参考文献】7頁
住宅火災の出火原因トップ5
つぎに、住宅火災における「出火原因」をみてみましょう。
『その他』の原因をのぞいて、もっとも多いのは『こんろ(16.3%)』です。
次いで『たばこ(11.6%)』『ストーブ(7.5%)』『配線器具(6.2%)』『電気機器(6.0%)』と続いています。
このデータを見ると、ガスコンロやたばこのように直接火をあつかうものだけでなく、コンセントのような配線器具も原因となって火災が発生していることがわかります。
※データ出典元:上記【参考文献】8頁
家庭内にひそむ住宅火災のリスク
ではあらためて、家庭内にある住宅火災のリスクについて確認しましょう。
ここでは先ほどの出火原因にも入っていた「こんろ」「ストーブ」「電気関係の火災」のほか、日常的に使う機会の多い「電子レンジ」、そして太陽光がもたらす「収れん火災」をとりあげます。
ガスコンロ調理|火のもとを離れた・消し忘れ
東京都が実施した調査によると、ガスコンロを「危険な使い方をした経験がある」と回答した人が『74.4%』と、高い割合を示しています(※1)。
具体的には「火がついているのにその場を離れた」という人が『54.4%』ともっとも多かったのです。
まさかと思うかもしれませんが、調査結果には「鍋をかけたまま寝てしまった」「突然の来客に対応して火を消し忘れた」などの事例がよせられています(※2)。
【参考文献】
※1:東京都生活文化局消費生活部『ガスコンロの安全な使用に関する調査報告書』平成28年2月/27頁・28頁
※2:同上/39頁
また、ガスコンロの使用中は着衣着火にも注意が必要です。
ストーブ|燃えるものが触れた・灯油に引火
住宅火災では「コンロ」「たばこ」に次いで多いのが「ストーブ」による出火です。
ストーブの熱源や石油ファンヒーターの吹き出し口に燃えるものが接触したことで、火災につながる事故がおきています。
また石油ストーブ(ファンヒーター)では、給油中の漏れた灯油にストーブの火が引火した事例もあるため注意しましょう。
【参考文献】PR TIMES(独立行政法人製品評価技術基盤機構)|小さなうっかりが大きな火災に ~「製品による建物火災」 原因トップ3~
電気火災|コードの断線・コンセントにホコリ
火災には電気が関係するものもあります。
たとえば重い物の下敷きとなり断線した電気コードが原因の火災や、コンセント部分にたまっているホコリがショートして出火することがあるのです。
新潟市では令和4年に発生した火災のうち、『電気関係によるもの(29件)』が『たばこ(20件)』や『ストーブ(13件)』を上回っていました。
【参考文献】NHK:新潟放送局|夏に多くなる電気火災に注意!火災の原因と対策をインタビュー
このように、直接火が見えない物による火災はほかにもあります。
電子レンジ|まちがった使い方による出火
昨今は電子レンジで簡単に調理できるさまざまな商品が販売されています。しかし電子レンジでは調理できないものもあるため注意が必要です。
たとえば、アルミホイルやペットボトルは電子レンジで使うことができません。
また、いも類のように水分が少ない食品を長時間加熱すると発火の危険があります。
電子レンジで調理する際は、商品の説明書を確認したり加熱しすぎないよう注意しましょう。
収れん火災|太陽光の屈折・反射
子どもの頃、虫メガネで光を集め紙を燃やす実験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。
このように太陽の光が屈折・反射することでおこる火災を「収れん火災」といいます。
過去には、室内にある化粧用ミラー(拡大鏡)や庭に置いてあったペットボトルに光があたったことで近くのものに着火・火災につながった事例があります。
とくに冬場は太陽の位置が低くなり、部屋の奥まで太陽の光が差し込むため、より注意が必要とされています。
【参考文献】消費者庁|鏡やガラス玉で起こる「収れん火災」に注意!-日差しが部屋の奥まで届く冬場に発生しています-
まとめ|住宅火災の原因を知り予防につなげよう
住宅火災は建物火災の1つであり、共同住宅よりも一般住宅で多く発生しています。
そしてその出火原因は、こんろやたばこといった直接火が見えるものだけでなく、電気火災や電子レンジのまちがった使い方によるもの、そして収れん火災もあることをお伝えしました。
本記事をひとつの参考として、住宅火災にはあらゆる原因があることを知り、火災予防の行動へとつなげていただけると幸いです。
【参考文献】
*コトバンク|火災とは
*東京くらしWEB|見えない炎で着火!? ~ガスコンロの近くには、燃えやすい物を近づけないで!~
*一般社団法人日本ガス石油機器工業会|ガスコンロ ヒヤリ事例集
(以上)