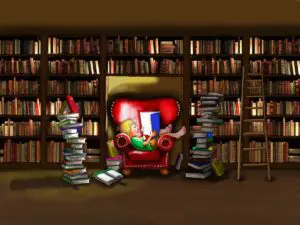本サイトはプロモーションが含まれています。
賃貸も地震保険に加入したほうがよい?メリットや注意点を理解して検討しよう
ライターの永野です!
大学生になって上京し、初めて1人暮らしをすることになったとき、「敷金?礼金?火災保険??????」と、初期費用の高さと当時の知識では意味不明だった内容に驚愕しました。火災保険なんて、加入する意味あるのかと思っていましたが、「お守り」として保険に加入しておくことの重要性は、その後10年くらい経って虫垂炎で入院したときにひしひしと感じました。
大きな地震が頻発する昨今は、火災保険と同時に、地震保険への加入を検討される方も多いようです。我が家も今の自宅を購入した際に確か加入した記憶ですが…賃貸物件も地震保険に加入する必要はあるのか、「そもそも加入できるのか」など、さまざまな疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。
購入・賃貸にかかわらず、地震保険への加入は可能です。今回は、賃貸物件にお住まいの方が地震保険に加入するメリットやデメリット、加入時の注意点などを解説します。
多くの賃貸物件で加入必須の火災保険
賃貸物件に入居する際は、火災保険に加入するケースが多い傾向です。賃貸契約をしたことがある方はわかるかと思いますが、契約時に支払う諸費用に火災保険料も含まれます。地震保険に関して解説する前に、まずは住宅の火災保険について基礎的な知識を確認しましょう。
火災保険とは
火災保険とは、火災で発生した損害を補うための保険です。民法では「失火責任法」といって、火災を発生させてしまった「失火者」に重大な過失がなければ、損害賠償責任を追わせないという決まりがあります。
失火者にとっては大変ありがたい法律ですが、こうして起こった火災に巻き込まれた側はどうでしょうか?隣の家や部屋の火災で自室も被害に合った場合、それを弁償してもらえないとなると…。非常に困りますよね。
そこで、火災による損害を補償してくれる火災保険が必要になるというわけです。
火災保険料の目安
火災保険料は、建物の評価や所在地、築年数、補償内容などによって決まります。1人暮らしの賃貸物件の場合は、1年につき3,500円~15,000円くらいが目安です。筆者の大学時代に借りていた1Kの賃貸物件は、2年で2万円ちょっとだった記憶があります。
非対応の損害もあるため注意
火災保険は火事だけでなく、落雷や水害などの自然災害、爆発事故などの人為災害などを幅広く補償してくれます。幅広い災害に対応し、いざというときに役立つ火災保険ですが、地震による損害、地震で発生した火災の損害は補償対象外です。
大地震が起こることが危惧されている昨今、地震への補償がないのは不安だと思う方も少なくありません。非対応の損害を補償するためにも、火災保険以外の災害保険への加入も検討しましょう。
火災保険・地震保険に関する詳しい情報は、災害保険に関する記事でもまとめています。
賃貸物件は地震保険に加入したほうがよい?
賃貸物件も地震保険への加入は可能ですが、「本当に加入したほうがよいのか」と迷う方もいるでしょう。地震保険への加入は必須ではないものの、できれば加入することをおすすめします。
地震保険加入をおすすめしたい方
地震保険への加入をおすすめするのは、以下に当てはまるような方です。
・大切にしている家財がある
・家財買い替えのための資金がない
代々伝わる高価な家具や、子どもの頃から大事にしている家具など、大切にしている家具がある場合は、加入をおすすめします。思い出の詰まった家財が戻ってくることは残念ながらありません。しかし、保険金が出れば経済面や精神面のダメージを軽減できるでしょう。
地震で家財が損害を受ければ、当然買い替えの必要があります。大型家電などは高額で、複数の家財を一気に買い換えるとなると、多額の資金が必要です。しかし、貯金があまりない方は買い替えが困難な場合もあります。現状貯金があまりないという方も、もしものときに備えて地震保険に加入するとよいのではないでしょうか。
無理に加入する必要はない
地震保険にはできれば加入することをおすすめしますが、加入は必須ではありません。ご自身の判断で「不要」だと思えば、加入する必要はないでしょう。
地震保険では地震そのものによる損害はもちろん、地震で起こった津波や火災での損害も補償されます。しかし、近くに海がない方は津波の心配はありません。また賃貸物件に住んでいる方のなかには「大切なものは実家にある」「寝るために帰るだけであまり家具・家電がない」という方もいます。
地震保険はいざというときに役立ちますが、保険料が負担になることもあるでしょう。加入するかどうかは、ご自身の状況によって判断するのが賢明です。
地震保険はメリット・デメリットを知って加入しよう
万一の補償として地震保険に加入したいと思ったら、メリット・デメリットを事前に把握しておくことも重要です。ここからは、地震保険加入で得られる利点、また注意点を確認しましょう。
地震保険のメリット
地震保険に加入するメリットは、大きく3点です。
・火災保険の補償対象外の部分をカバーできる
・耐震等級が高いと割引が適用される
・税金の控除が受けられる
火災保険は前述の通り、さまざまな災害による損害を補償してくれます。しかし、地震や噴火、津波、地震による火災は補償対象外です。地震保険に加入すれば、これらをカバーでき、どのような災害にも対応できます。
また建物には耐震等級があり、耐震等級2は30%、3なら50%の割引が適用されます。さらに、保険料は「地震保険料控除」の対象です。所得税で最大5万円、住民税で2.5万円控除されますので覚えておきましょう。
地震保険のデメリット
地震保険はさまざまな補償や割引がありますが、一方で以下のようなデメリットがあることも覚えておく必要があります。
・火災保険プラスアルファの保険料がかかる
・単独加入は基本的にできない
・地震保険のみですべての損害を補償することができない
地震保険は基本的に、単独で加入することができません。火災保険とセットで加入する必要があり、当然そのぶん保険料が上がります。また、地震保険のみですべての損害を補償することはできません。火災保険との組み合わせで損害をまかなうという意味でも、セットでの加入が求められます。
賃貸物件で地震保険に加入する際のポイント
地震保険への加入を決めたら、どの保険会社にするかを検討しましょう。よりよい保険会社を選ぶために注目したいポイントは、大きく3点です。
保険料
地震保険や火災保険に限らず、各種保険は分からない方にとっては補償内容が複雑で、どれを選べばよいか迷うこともあるでしょう。保険料が相場より非常に高い、安い地震保険には注意が必要です。
地震保険の保険料は建物の立地や大きさ、耐震構造などにもよるため相場は一概にはいえません。都心部の戸建て(非耐震構造)の場合は1年で25,000円、耐震構造の戸建てやマンションは17,000円ほどだといわれています。賃貸物件の保険料は広さなどにもよりますが、戸建てより安く住むのが一般的です。
加入内容
地震保険の加入内容にはさまざまなものがありますが、賃貸物件の場合は家財のみでもじゅうぶんだといえます。建物部分は物件のオーナーが所有しているため、居住者が保険で補償する必要はありません。
家財のみの補償では、家具類や家電製品が対象となります。車や高価な貴金属、絵画、骨董品などは対象外となるため注意しましょう。
補償金額
実際に受けた損害の満額を、地震保険として受け取ることはできません。付帯する火災保険の30~50%が契約金額となっています。また、家財の補償の上限は1,000万円ですので、こちらも注意しましょう。
地震保険で受け取れる保険金は、損害状況によって変わります。全損の場合は契約金額の100%、半損壊は規模により30~60%、一部損壊は5%です。これ以下の場合は保険金が支払われないことも、覚えておく必要があります。
賃貸物件の地震保険は状況によって加入しよう
賃貸物件は契約時に火災保険に加入するのが基本です。地震保険は、火災保険でカバーできない損害を補償してくれるので、賃貸物件に住む方にもおすすめだといえます。加入は家財のみでじゅうぶんです。
加入の有無は補償内容や契約金、ご自宅の立地や経済状況などから総合的に判断しましょう。よりよい地震保険に加入し、いざというときに役立ててくださいね。
編集後記
私は保険に関しては知識ほぼ皆無で、自動車保険も生命保険も何もかも、ほぼいわれるがままに加入しています。火災保険も、夫の知り合いの方にお願いしており、状況が謎だったりそうじゃなかったり…。
ただ、学資保険だけは自分で検討して、「これがいいかな」と思ったものを選びました。今回の内容とはあまり関係ありませんが(笑)。
「保険をかける」という言い回しがあるように、いざというときに代わりになるものや役に立つものがあるのは、どういった状況でも大切です。火災保険や地震保険も、内容があいまいにしろないよりあったほうがよいのは確かですが、こういったテーマに関わらせていただく身である以前に、「子や家を持つ1人の社会人」としてまだまだ勉強しなければいけないなぁと思うのでした。
参考サイト
・賃貸は火災保険で十分?地震保険が必要かどうかを考える
・地震保険は賃貸でも加入すべき?
・賃貸物件で契約した火災保険。地震保険も付けておいたほうがよい?
・わが家は加入すべき?地震保険のメリットデメリットをFPが徹底解説