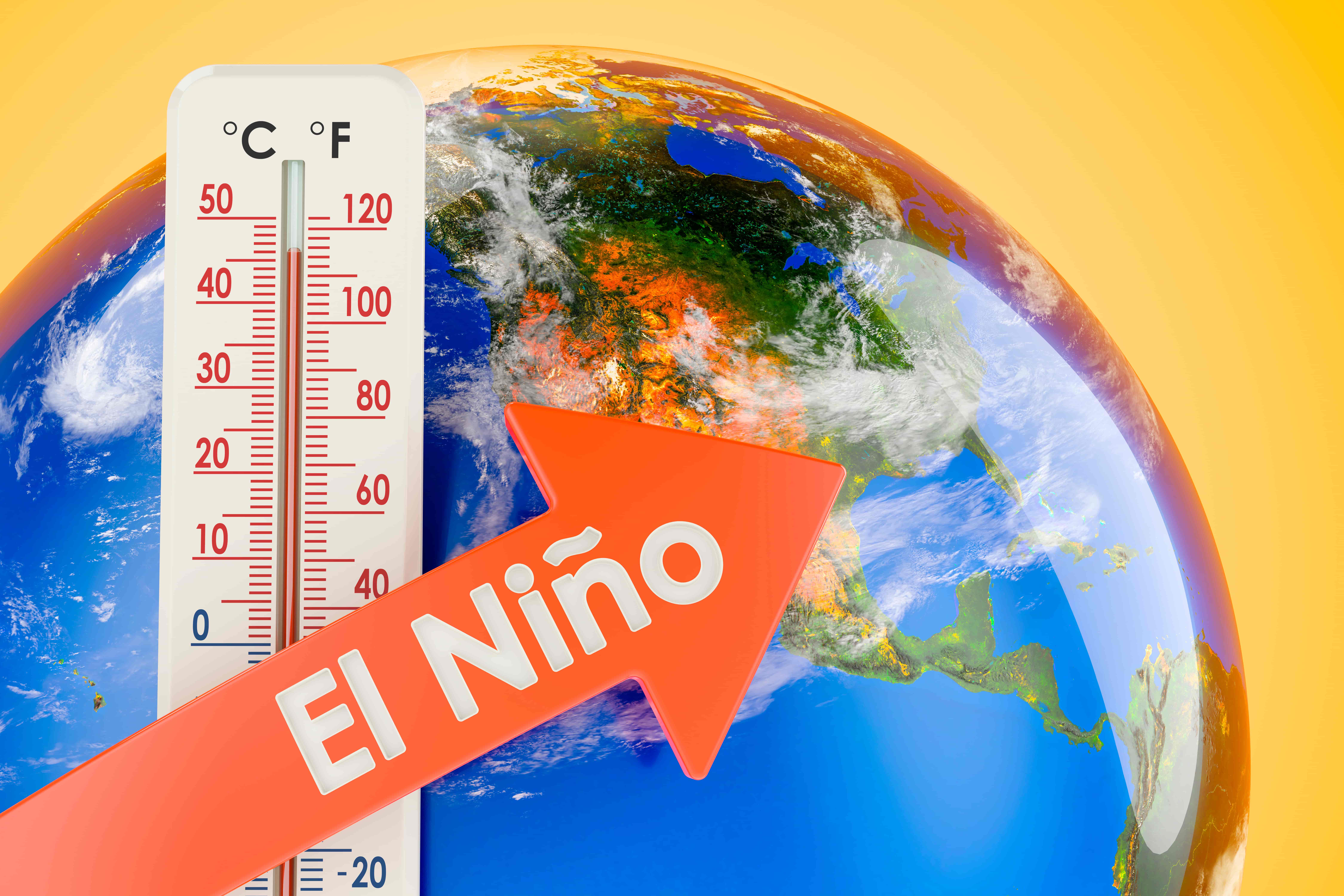本サイトはプロモーションが含まれています。
「インクルーシブ防災」を、いち防災士として考えてみた!
インクルーシブ防災と呼ばれている言葉をご存じでしょうか?
インクルーシブ防災とは、障がい者や高齢者の方などを含めて、誰も取り残さない防災との意味を持っている言葉です。
SDGsの取り組みの中に「インクルーシブ」との単語はよく使われていて「SDGs×インクルーシブ防災」として取り上げられるシーンも多くなってきました。
今回は、誰も取り残さない防災を、いち防災士として考えてみました。
インクルーシブとは「排除しない」の意味を持つ単語
まず、インクルーシブとの単語の意味から確認してみましょう。
「インクルーシブ=排除しない」との意味を持つ単語であり、そのほか「支え合う」や「一緒に」などに解釈されることが多いです。
英語ではInclusion(インクルージョン)
インクルーシブの意味を調べると、さまざまなサイトがヒットします。
ヒットしたサイトを確認すると、概ねこのような解釈がされています。
確認したサイトの中で最もしっくりきたのが「インクルーシブふくおか」であり、このサイトでは次のように解釈されていました。
英語で「エクスクルージョン(exclusion)」=「排除」の反対語が「インクルージョン(inclusion)」。つまり、「排除しない」ってことだよ。
インクルーシブふくおか
イラストを拝借して解釈すると「みんな一緒」
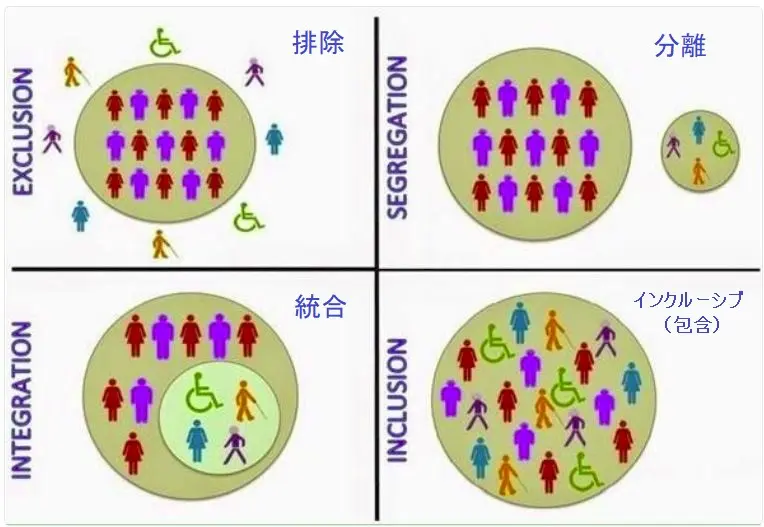
このイラストの右下が、インクルーシブとなり障がい者や高齢者を含めた「みんなが一緒」なイラストになっています。
インクルーシブ防災とは「誰も取り残さない防災」のこと
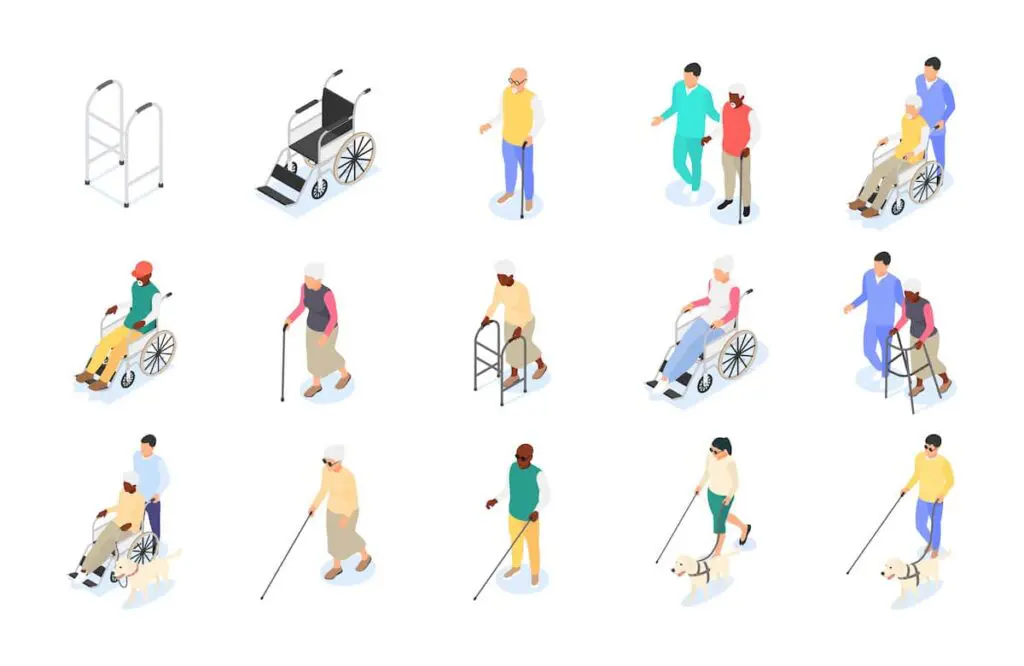
では、先に確認した「インクルーシブ」の単語を使った「インクルーシブ防災」とは、どのような内容であるかというと『誰も取り残さない防災』となってきます。
もうひとつピンときませんね・・なので、具体的に見てみましょう。
障がい者や高齢者を含むあらゆる人を取り残さない防災
『誰も取り残さない防災』をもう少し具体的にすると、障がい者や高齢者を含むあらゆる人を取り残さない防災と、いうことになってきます。
前職で自治体の防災計画の策定をサポートしてた時には、災害弱者と呼ばれる障がい者や高齢者、妊婦、子どもなどに向けた計画も策定していました。
10年以上防災に携わってきた中で、防災で使われる言葉も「災害弱者⇒災害時要援護者⇒避難行動要支援者」と変化してきたのも事実です。
では、最新の言葉となる「避難行動要支援者」とは、どのような方を指しているのでしょう。
避難行動要支援者とは「災害時に自ら避難することが困難な者」
防災計画の中で使われている、避難行動要支援者(旧災害弱者)とは「災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者等の避難行動要支援者」と定義されています。
つまり、インクルーシブ防災が意味するところの「障がい者や高齢者を含むあらゆる人を取り残さない防災」に、合致してくるのです。
インクルーシブ防災は既に防災計画に取り込まれていた
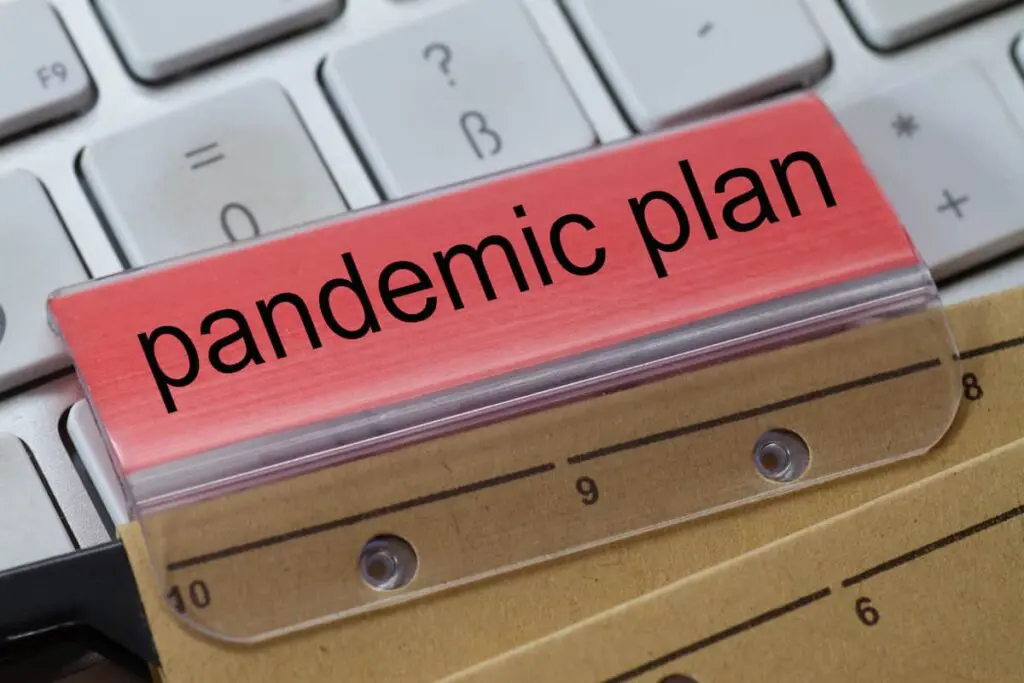
先の流れからいくと、SDGsが盛んに叫ばれる昨今にて「インクルーシブ防災」との単語が、よく取り上げられるようになってきています、
ですが、実は既に防災計画の中では「避難行動要支援者」として、障がい者や高齢者など誰も取り残さない防災は、計画されているのです。
防災計画では「障がい者と高齢者だけ」インクルーシブ防災とは違う
ところが、前述のようなことをいうと「防災計画でいう避難行動要支援者は、障がい者と高齢者だけじゃないか!インクルーシブ防災はそれらを含めて、全ての人を救うことをいっているのだ」と反論されてしまいそうですが・・そうではありません。
避難行動要支援者は全ての人が含まれている
例えば、インクルーシブ防災で全ての人を取り残さないといっても、自力で避難できる方までを救助対象にはしていないはずです。
もしも、自力で避難できる全ての者を含むのであれば、自衛隊も警察も消防レスキューですら、救助対象となり誰も助けることはできなくなるはずです。
少し極論になってしまいましたが、でも、そういうことになるでしょう。従って、インクルーシブ防災でも救助対象は「自ら避難できない全ての者」となるはずなのです。
そうなれば、避難行動要支援者が意味する支援者(救助対象者)と、同じことになるではありませんか。
防災では分かりづらい言葉が多いと感じる
防災士として、これまで防災計画策定などに携わってきた者として常々感じるのは「防災では分かりづらい言葉が多い」ことです。
これらの言葉の意味を正確に覚えるには、専門的な知識がないとまず無理です。
今回のテーマである、インクルーシブ防災もそうです。内容を確認すれば先ほどから解説しているとおり、防災計画上の避難行動要支援者の定義と同じとなりますからね。
いち防災士としての結論は、行政が使う言葉かそうでないか!
インクルーシブ防災を考えた結果、いち防災士として出した結論は次のとおりです。
避難行動要支援者は防災計画を策定する行政が使う言葉
まず、避難行動要支援者については「防災計画を策定する行政が使う言葉に限られる」ということ解釈します。
一般の方が行政が公開している防災計画に目を通すことは、ほぼないといっていいでしょう。
仮に目を通したとしても、直ぐに読むのを諦めるはずです。その理由は、難しい言葉と文章を使って作成されているからです。
従って、避難行動要支援者が「障がい者や高齢者など、自ら避難することが難しい者」であることが、広く世の中に浸透しなかったということです。
インクルーシブ防災は世の中一般な人が使う言葉
一方で、インクルーシブ防災は行政ではない、世の中の一般的な人が使う言葉で「誰も取り残さない防災」として、広まるといいと感じています。
同じ意味でも「避難行動要支援者をひとりも取り残さない防災計画を遂行する」というよりも「インクルーシブ防災で、誰も取り残さない防災を行なおう」のほうが、分かりやすく広まりやすいのは確かです。
防災は分かりやすい言葉の方が広がりやすい
今回はSDGsでよく使われるようになったインクルーシブ防災について、いち防災士として考えたことを記事にしてみました。
誰も取り残さない防災は、実は既に自治体の防災計画には記載されていることなのです。ただ、難しい言葉で表現しているから広く伝わっていないだけ。
同じ意味であるインクルーシブ防災が広まれば、それが一番でしょう。
防災はみんなの命をみんなで守ることが基本ですから、分かりやすい言葉を国も使って欲しいと改めて感じました。