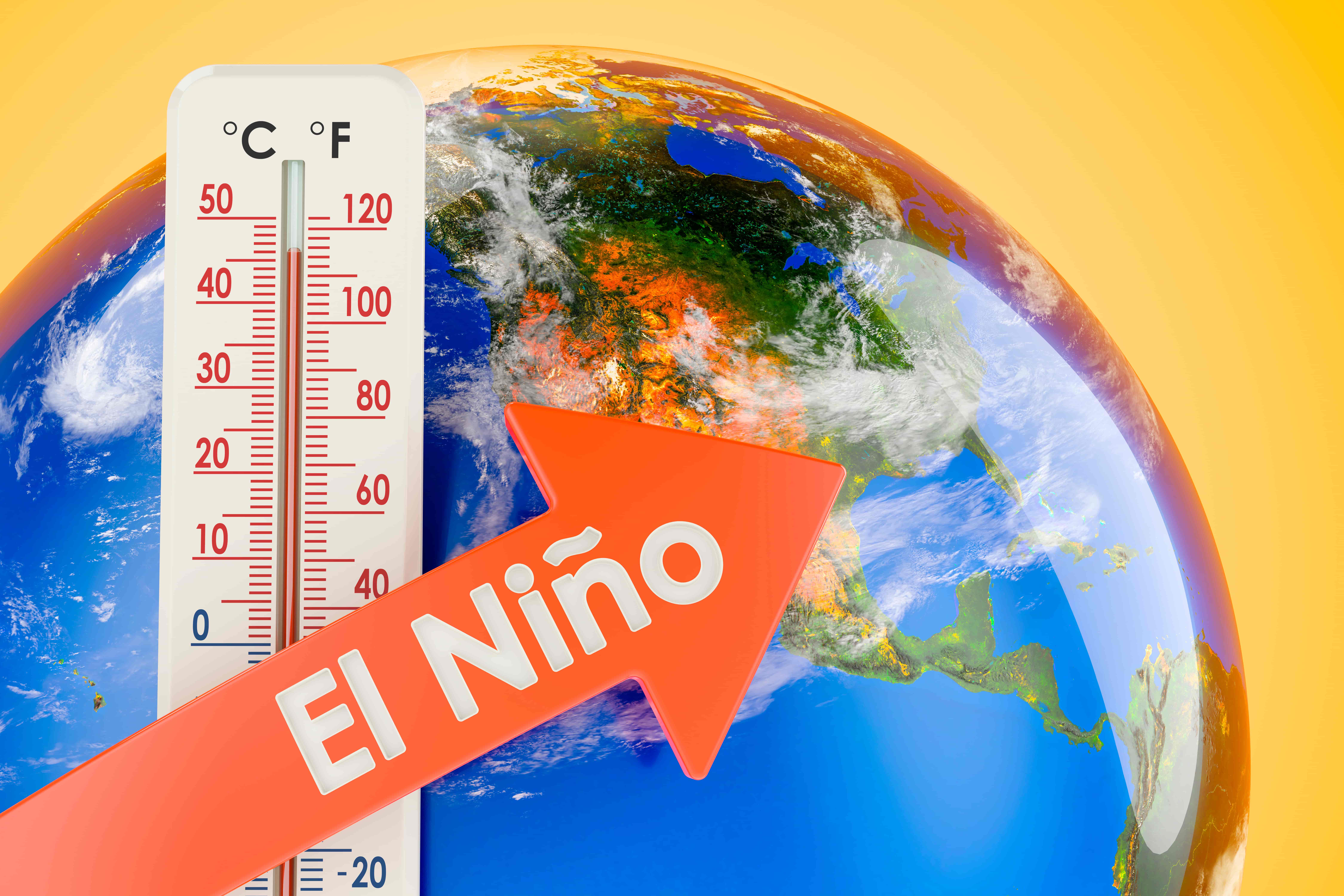本サイトはプロモーションが含まれています。
室内でのこどもの転落に注意!できる対策を知ろう
こどもの怪我の原因として多くあげられるものの1つに転落があります。動き始めた赤ちゃんや小さなこどもは何にでも興味津々。大人が思いもよらない方法で高いところに登り、大きな事故につながる危険性があります。
今回は、自宅で転落が起こる理由やもしものときの対処法、事前にできる対策などを見ていきましょう。
こどもの転落事故、多いのは?
消費者庁の調べによると、2014~2018年の5年間のあいだに起こった転落死事故は92件。およそ半数が0歳から4歳の子どもだったそうです。もっとも多かったのは3歳児の18件で、次いで4歳児が14件、1歳児が5件でした。
転落事故が起こりやすいのは窓やベランダなどで、特に春から夏のように窓を開け放しておくことの多い時期には、事故が増加する傾向です。
こどもの転落はなぜ起こる?
こども、といっても幼児のような小さなこども、小中学生くらいのある程度年齢を重ねたこどもとでは、転落の原因は異なります。それぞれ、なぜ事故が起こるのかを解説します。
幼児の場合
幼児の転落事故の原因は、大きく2つです。1つは大人が目を離しているとき、もう1つは足がかりになるものがあるときです。
幼児の転落事故の傾向として、保護者が少し目を離しているあいだに起こりやすいという点があります。加えてベランダや窓からの転落は、足場になるようなものが置いてある場合に起こりやすいです。
小さなこどもは椅子やテーブル、荷物などを足がかりにして窓やベランダの手すりなどによじ登り、転落してしまう恐れがあります。また、こうした大きな転落以外にも、いすやテーブルから転落する、踏み台から転落するなどして小さなケガをしてしまうこともあるので注意が必要です。
小学生の場合
小学生が転落する原因は、小さなこどもとは異なります。小学生の転落事故は、遊んだりふざけたりしている最中に起こることが多いです。
たとえば追いかけっこやかくれんぼなどをしていてマンションや学校のベランダや通路から転落してしまう、窓枠に座って話していたらバランスを崩して落ちてしまうという事故は多く起こっています。
ある程度成長したこどもの転落事故を防ぐためには、危険な遊びをしない、危険な場所に近づかないといったことを、小さな頃から日常的にこどもに教えておくことも重要です。
こどもが転落した場合の対処法は
大人がどれだけ注意を払っていても、不慮の事故が起こってしまうことはあります。もしこどもが転落をしてしまったら、どのように対処すればよいのでしょうか。
全身をチェックする
まずは全身を細かくチェックしましょう。転落をはじめさまざまな事故の際には「頭をぶつけていないか」を最重視する方が多いです。しかし、頭以外の部分にも、出血や腫れ、打撲、骨折などの怪我を負っている可能性があります。
必要に応じて病院に行く、救急車を呼ぶ
手足や胸、お腹など全身をよくみて、おかしいなと思う部分があれば必要に応じて病院へ行きましょう。一刻を争うような状態であれば、迷わず救急車を呼んでも構いませんが、急を要するような様子でなければかかりつけの病院に連絡し、診察をしてもらいます。
救急車を呼ぶかどうか迷ったら、子ども医療電話相談「#8000」に電話をして症状を伝え、指示を仰ぎましょう。転落は命に係わるようなけがをしている可能性もあるので、「これくらいなら大丈夫だろう」と思わず、少しでも気になる部分があれば、必ず病院を受診してください。
転落後数時間はとくに注意して観察する
転落後はこどもの様子をよく観察する必要があります。特に、転落後数時間はより注意をしながら変わったことがないか見ていてください。転落後すぐは平気そうでも、時間が経つにつれて不調があらわれる場合もあります。
1~2日は様子をみる
こどもが転落してしまったあとは、数時間は特に注意をして、その後1~2日もいつもよりじっくりとこどもの様子をみてください。元気がない、食欲がない、嘔吐をするなどの症状が見られたら、すぐに病院へ連れていきます。
むちうちなどは表面的にわかる症状がなく、時間が経つにつれて不調が増す場合もあるので、不調が改善されるようしっかりとケアをしてあげてください。
乳幼児の転落を防ぐためにできる対策
小学生のこどもには日頃からの指導で危険な場所で遊ばない、ふざけないといったことを何度も指導していくことで、転落事故の可能性を低減させることができます。
では、まだ言葉があまり通じず、危険な場所にもどんどん突き進んでいく乳幼児はどのように転落を防止していけばよいのでしょうか。最後に、転落を防ぐためにできる対策をご紹介します。
踏み台になりそうなものを置かない
最も重要なのは、踏み台になりそうなものを窓の近くやベランダに置かないことです。エアコンの室外機や椅子、手洗い用の台、おもちゃ箱など、踏み台になるものは部屋中にあふれています。
踏み台になりそうなものを全て撤去することは難しいかもしれませんが、やむを得ず大人が少し目を離すあいだは、そういったものをできるだけ窓などから遠ざけるようにしましょう。
階段には柵をつける
階段からの転落も、大きなけがにつながるので注意が必要です。階段の上と下には柵をつけ、こどもが自力で昇り降りできないようにしましょう。また、この柵はしっかりと固定し、こどもが揺らしたりぶつかったりしても取れないようにしておくことも大切です。
筆者の自宅でも柵をつけていましたが、たまたま筆者が2階に用事があって柵の扉を開けたところ、衝撃で外れてしまったことがあります。もしこどもだけが2階にいて、ママを呼ぶために柵を揺らしたりしたら…と思うとゾっとしましたが…
きちんと固定していても、開け閉めしているあいだに固定している部分が緩まってしまうこともあるので、日常的なチェックも忘れないようにしましょう。
窓などにもロックをしっかりつける
窓にはしっかりと鍵をかけ、できればプラスアルファのロックをつけておくとよいです。こどもは大人が思っている以上に賢いので、鍵の開け方を覚え、勝手に開錠してしまうこともあるでしょう。
後づけのロックを使用すれば、こどもがもし窓の鍵を開けてしまっても、窓を開けて身を乗り出してしまうといったことを避けられます。
高いところに登らない、遊ばないよう教える
言葉が通じない、といっても小さなうちから高いところに登ってはいけないことを地道に教えておくことも大切です。ジェスチャーやイラストで教える、もし高いところに登ってしまった場合にはいけないことだと言葉や態度で伝えるようにします。
小さなこどもの教育方法や方針はさまざまですが、命の危険に関わることはある程度厳しく教えていくことも大切です。もしこどもが高いところに登ってしまったらどのように伝えていくか、大人同士で話し合い家庭の方針を決めていきましょう。
危険だと思う場所では目を離さない
どれだけ対策を施しても危険をゼロにすることは難しく、また外出先などで転落の恐れがあるシチュエーションに出くわすこともあるかもしれません。そんなときは、とにかくこどもから目を離さず、転落事故を防ぐことも重要です。
こどもから1秒も目を離してはいけない、ということはありませんが、大人同士で集まって話したりしていると、ついついこどもへの意識は薄れがちです。そういった数秒、数分のあいだにこどもがいたずらをしたり、大きな事故を起こしたりするケースも少なくないので、転落も含めやけどや誤飲、転倒などさまざまな危険を予想しながら、しっかりとこどもを観察してください。
対策を施し、転落事故を防ごう
転落はもちろん、こどもに降りかかる事故の多くは「起こる可能性がある」ということを前提に考えておく必要があります。「これくらいなら大丈夫だろう」と思わず、「少しやりすぎかもしれない」と思うくらい対策を施しても問題はありません。
納得のいく対策や指導で、転落事故を防いでいきましょう。