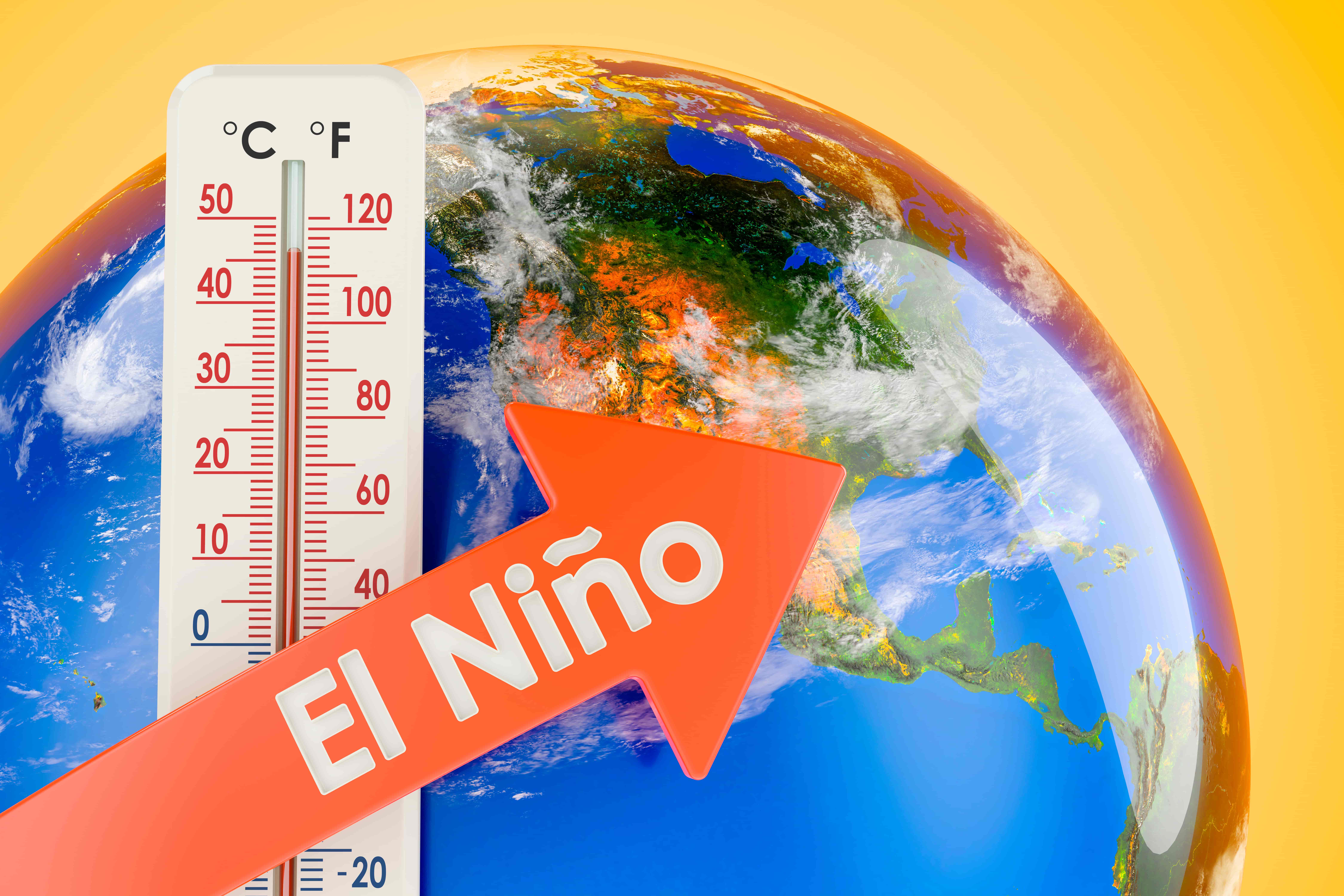本サイトはプロモーションが含まれています。
1986年伊豆大島噴火では「割れ目噴火」の発生で島外避難
日本には111の活火山があり、そのうち21の火山が東京都に存在しています。
そのなかの8つの島に住民が住んでいるのですが、今回は1986年11月に伊豆大島で発生した噴火をとりあげます。
この噴火では「割れ目噴火」とよばれるものがきっかけとなり、全島民が島外へ避難する事態となったのです。
本記事ではこの「1986年伊豆大島噴火の概要」と「過去の噴火活動」、そして「伊豆大島の噴火警戒レベル」についてお伝えします。
さらに「噴火情報を入手できるサイト」もご紹介するので、この機会にぜひアクセスして、災害に備える行動へとつなげましょう!
伊豆大島の概要
はじめに、伊豆大島について簡単に確認しましょう。
伊豆諸島で最大の島
伊豆大島は東京都大島町にある活火山で『全島面積91平方キロメートル』という、伊豆諸島で最大の有人島です。
『東京から120キロメートル、熱海から46キロメートル』であり、温泉やさまざまなレジャーも体験できる観光地です。
【参考文献】東京都大島町公式サイト
海底火山として誕生
伊豆大島は今から数万年前に海底火山として誕生しました。
そして、たび重なる激しい噴火によって火口周辺には噴出物がたまり、火口が海面から出現したのです。
現在の島の形はおよそ2万年前にできたとされています。
【参考文献】伊豆大島火山防災連絡事務所|伊豆大島火山について
三原山|山頂のカルデラ内にある小さな火山

伊豆大島の頂上には、巨大噴火によってできた凹地(=カルデラ)があり、さらにその南部には伊豆大島で最高点となる中央火口丘(かこうきゅう)の三原山(標高758)が存在しています。
中央火口丘とは『おおきな火口やカルデラ内に新たに生じた小火山※』のことです。*goo辞書|中央火口丘より引用
三原山もトレッキングや火口周辺の絶景が見られるなど、観光スポットになっています。
1986年伊豆大島の噴火
それでは、1986年(昭和61年)に発生した伊豆大島の噴火についてみていきましょう。
現場を取材した報道映像
はじめに、1つの動画をご紹介します。
それは、ANNnewsCHが公開している、伊豆大島の噴火を取材したときの映像(2分52秒)です。
ここには、取材者たちへ避難指示が出された直後の状況や急いで車に乗り込む人の姿、そして、オレンジ色のマグマが空高く立ち上るなか、住民が船での避難にむかう様子が映しだされています。
まさに緊迫した状況が伝わってくる映像です。
火口ではない所からマグマが噴出

1986年伊豆大島の噴火の特徴として「割れ目噴火」があげられます。
割れ目噴火とは『地盤に生じた割れ目を通して溶岩が噴出する形式の噴火※』であり、伊豆大島では実に565年ぶりに発生したのです。※goo辞書より引用
11月21日に発生した割れ目噴火では溶岩が『高度約1,500mまで達し』、その高さは世界最高値とされています。※参考/伊豆大島ジオパーク ジオサイト「1986年割れ目噴火 B火口列」
島民・観光客は島外避難
この噴火は16時15分・17時46分と続いて発生しました。
そして、溶岩流が島の中心部へと迫ってきたことで全島民および観光客に対して島外避難指示がだされたのです。
島民およそ1万人と観光客2千人が下田や東京など、各地でおよそ1か月避難生活を余儀なくされました。
火山活動の経緯
ここで、この噴火の経緯を簡単にまとめます。
主な活動は、次のとおりです。
◇1986年伊豆大島噴火の活動概要
| 月日 | 主な現象 |
|---|---|
| 11月12日 | 噴気が上がっているのが目撃される |
| 11月15日 | 噴火が始まる(A火口列) |
| 11月19日 | 火口からあふれた溶岩が流れ下る |
| 11月21日16時15分 | 割れ目噴火が始まる(B火口列) |
| 11月21日17時46分 | 新たな割れ目噴火が始まる(C火口列) |
| 11月21日18時頃 | 溶岩が流れ下り始める |
| 11月21日夜 | 全島民に島外避難命令がでる(およそ1か月、島外での避難生活となる) |
噴火がおさまったと思われていたなか、21日に割れ目噴火が発生したのです。
最初に噴火があった11月15日から活動がおさまる23日までの噴出物量は『約6~8千万トン』と推定されています。
【参考文献】気象庁 伊豆大島火山防災連絡事務所「伊豆大島火山について」
では、伊豆大島ではこれまでどれほどの噴火がおこってきたのでしょう。
伊豆大島噴火の歴史
ここでは、気象庁の資料をもとに、1986年の噴火と同じ“中規模”の噴火をとりあげてまとめます。
中規模の噴火をピックアップ
◇伊豆大島における中規模の噴火歴(1821年以降)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1821年 | 文政4年 |
| 1822~24年 | 文政5~7年 |
| 1876年~77年 | 明治9~10年 |
| 1912~14年 | 明治45~大正3年 |
| 1922~23年 | 大正11~12年 |
| 1950~51年 | 昭和25~26年 |
| 1986年 | 昭和61年 |
気象庁によると、伊豆大島における中規模の噴火の間隔は『36~38年』だとされています。
そして、伊豆大島は活火山のなかでも24時間体制で火山活動を監視する「常時観測火山」に指定されているのです。
【参考文献】気象庁|伊豆大島
あらゆる機器で24時間観測
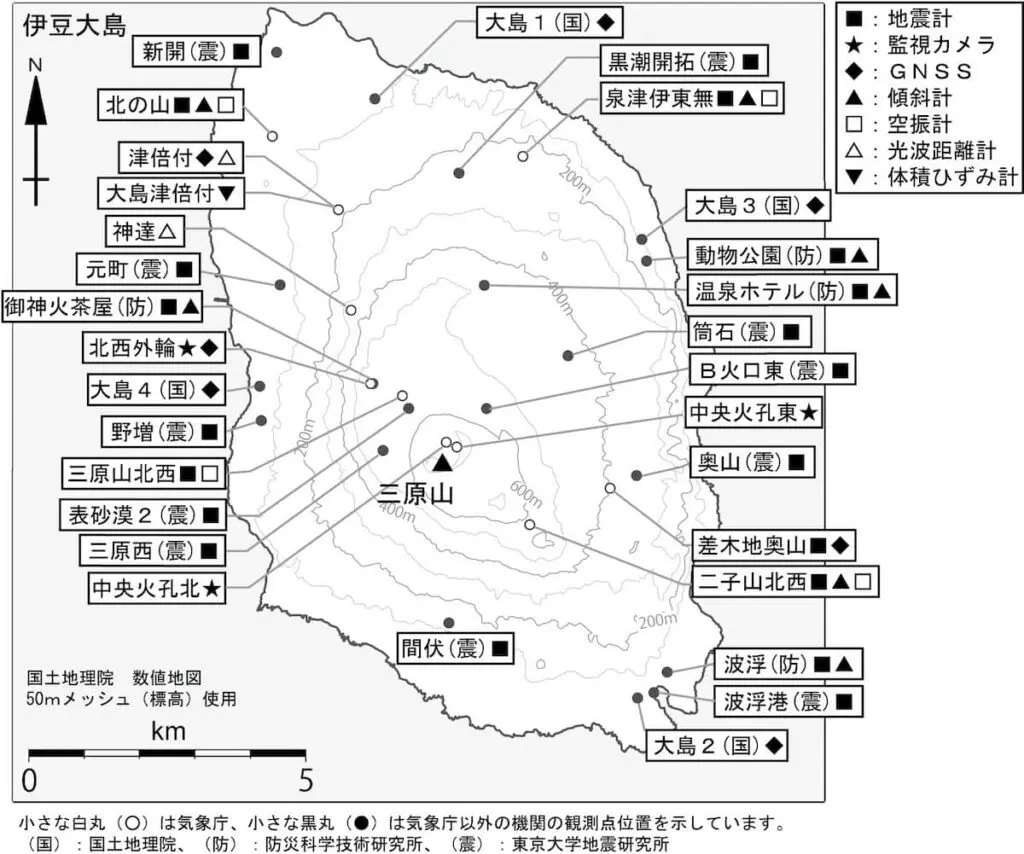
上の画像は気象庁のサイトのなかで、伊豆大島にある観測機器を地図上に示したものです。
たとえば、地震計は5箇所・監視カメラは3箇所あります。
そして、このように常時観測して得られたデータをもとに、噴火活動に応じた情報が発信されるのです。
伊豆大島の噴火警戒レベルを知る
噴火警戒レベルとは、警戒が必要な範囲と住民等がとるべき行動を5段階で示したものです。
各火山ごとに作成されており、気象庁のサイト「各火山のリーフレット」からみることができます。
伊豆大島の噴火警戒レベルから、その一部をお伝えしましょう。
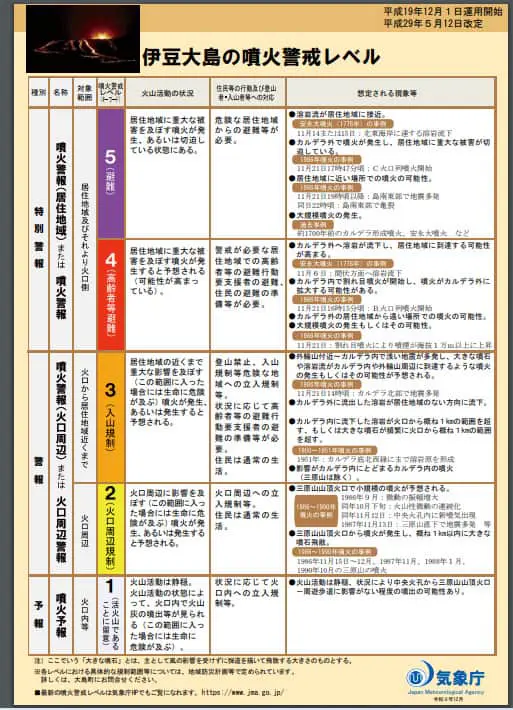
たとえば、「噴火警戒レベル2(火口周辺規制)」では『火口周辺への立入規制等』がなされるものの、『住民は通常の生活』を過ごすことができるとされています。
そして「噴火レベル3」では『登山禁止』となり、『状況に応じて高齢者等の避難行動要支援者の避難の準備等が必要』となっています。
詳細は、こちら(伊豆大島の噴火警戒レベル)でチェックできるので、ぜひご確認ください。
登山者向けの情報をチェックして自然を満喫しよう!
活火山は噴火という災害をもたらすことがある反面、わたしたちに多くの恵みを与えてくれます。
伊豆大島にも温泉や自然の美しい景観のほか、島内に咲く椿(つばき)の花は国内最高クラスとされるなど、たくさんの魅力があふれています。
しかし活火山である以上、噴火への備えは不可欠であり、わたしたちは正しい情報を知っておくことが大切です。
そこで役立つサイトの1つが、気象庁「火山登山者向けの情報提供ページ(全国)」。
ここでは「最近1週間以内に情報を発表した火山」や、毎月だされる「定期的に発表する情報」がチェックできます。
ぜひこれらも活用して災害に備えながら、日本の自然を満喫してくださいね。
【参考文献】
*東京都防災ホームページ|東京都の火山
*気象庁|伊豆大島
*YAHOO!JAPAN 災害カレンダー|伊豆大島三原山大噴火 全島民が島外避難(1986年)
*気象庁 伊豆大島火山防災連絡事務所|伊豆大島火山について
*伊豆大島ナビ
*伊豆大島ジオパーク
(以上)