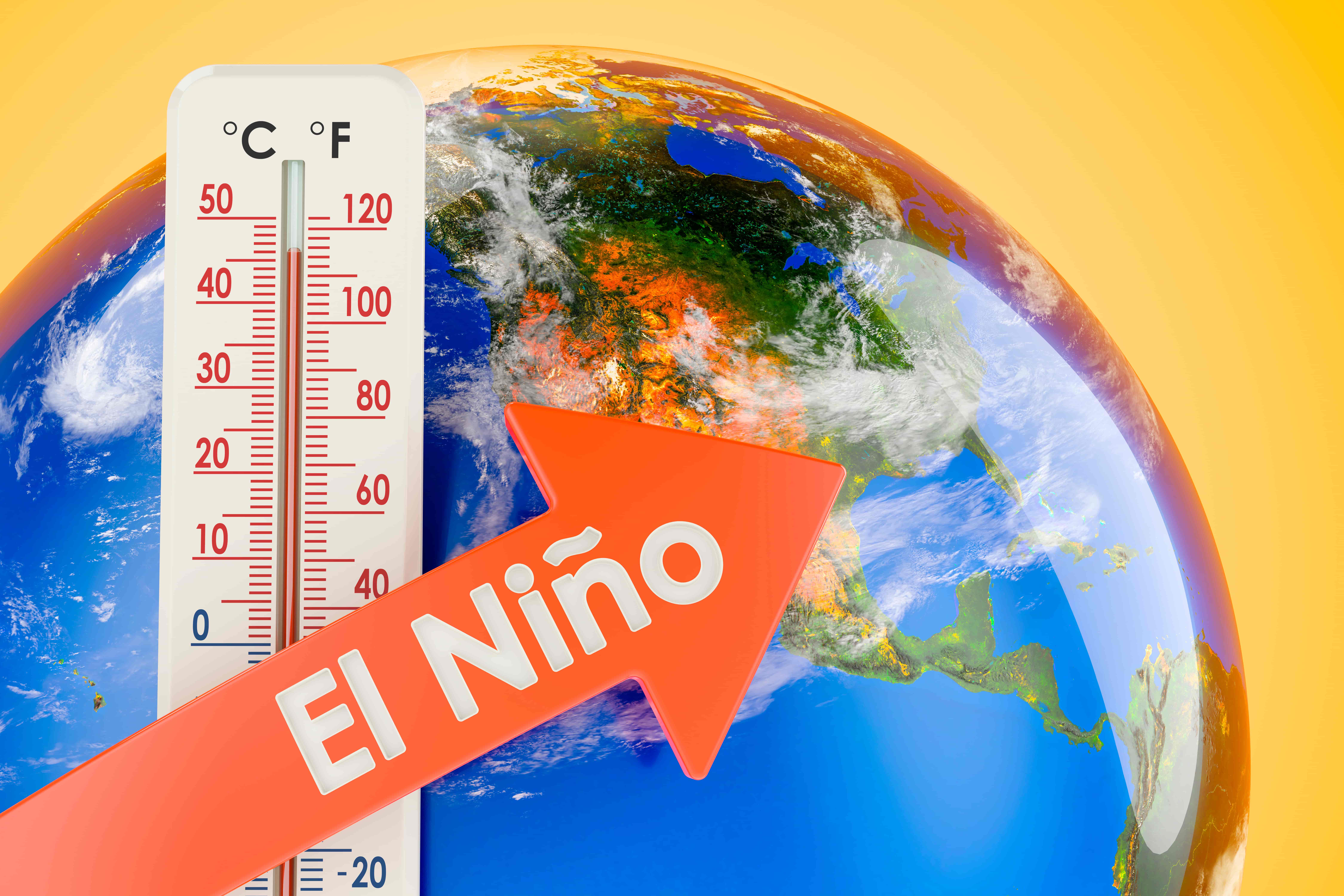本サイトはプロモーションが含まれています。
心肺蘇生法やAEDの使い方が学べる応急処置の正しい方法とは?
応急処置という言葉には、急なケガや病気に対する手当てという意味がありますが、「心肺蘇生法」や「AEDの使用」といった救急救命の処置を連想する人も多いでしょう。学校の授業や運転免許の講習などでも習う応急処置ですが、万一のときに「習ったのが昔過ぎて忘れてしまった」では意味がありません。
今回は、応急処置の目的や方法、応急処置を学べる場所はどこかなどをご紹介します。
応急処置とは呼吸や心拍を回復させる処置
応急処置は呼吸や心拍が停止してしまった人に対し、回復するような処置を行うことです。胸骨圧迫(心臓マッサージ)や人工呼吸、AEDの使用などを応急処置、救急救命と呼びます。
しかし、厳密にいうと応急処置は、救急隊員が行う手当てなのだそうです。私たちが連想する「一般市民による手当て」は本当は応急手当(おうきゅうてあて)というそうですが、この記事では一般市民による処置のことを「応急処置」と呼ばせて頂きます。
応急処置の目的と重要性
応急処置の目的は「症状を悪化させないこと」です。道端で突然人が倒れたり、事故や災害でけが人が出たりした場合、医療行為のできる助けが来るのを待つ時間が発生します。
軽症の場合は救急車などを待つことができますが、なかには一刻を争うような症状の方もおり、そんな方が症状を少しでも悪化させず、助けを待てるようにするのが応急処置です。
応急処置は医療行為ではないため、資格や経験がなくても誰でも行うことができます。一時的な措置ではありますが、人命を守るための大切な行為ですので、多くの人が応急処置の正しい方法を知り、いざというときに備えることが重要です。
応急処置で命が助かる可能性が上がる
心肺停止状態にある人は、時間が経過するにつれ存命率が下がります。つまり、何もしないまま救急車を待っていると、死亡する可能性が高くなってしまうのです。
命が助かる可能性は心肺停止後2分で25%程度、10分後には10%を切ります。
しかし、救急車を待っているあいだに誰かしらが応急処置を施せば存命率はアップし、2分後で50%以上。10分後でも20%ほどの確率で助かるというデータが出ています。
周囲の勇気ある行動で命を救うことができるならば、と考えると、ぜひ応急処置の方法を知っておきたいと思いませんか?
応急処置の方法とポイント
ここからは、応急処置の方法を説明していきます。応急処置の際は注意点をよく理解し、手順を守って行いましょう。
応急処置の際の注意点
応急処置を行う際は、以下の点に注意が必要です。
- 1人で行おうとせず、必ず周囲に指示や助けを求める
- 周囲に人がいない場合はまず119番通報し、救急車を呼ぶ
- 応急処置をする前に安全な場所へ移動し、自身の身も守る
- 人工呼吸の際は感染リスク低減のためにマウスシールドなどを使用する
また、応急処置をしたからといって必ずしも心肺停止状態の方の命が助かるとは限りません。応急処置が成功すればよいですが、さまざまな方法を試しても、命を救えない場合があることも想定しておきましょう。
せっかく応急処置をしても残念な結果となってしまった場合、「助けられなかった」「私が命を奪ってしまったかもしれない」と自分を責めてしまう方もいらっしゃいます。そうなることを恐れ、何もできなくなってしまうこともあるかもしれませんが、勇気をもって応急処置に当たることも大切です。
応急処置の手順
応急処置の手順は次の通りです。
- 意識の確認
- 意識がない場合、周囲の人に119番通報とAEDを持ってくるよう依頼
- 呼吸の有無を確認
- 呼吸がない場合、気道を確保し胸骨圧迫をする
- 人工呼吸をする
- AEDを使用する
胸骨圧迫・人工呼吸・AEDの使用は、正しい知識がないとできません。1つずつ手順を見ていきましょう。
胸骨圧迫の方法
胸骨圧迫をする際は、まず傷病者を平らな場所に仰向けに寝かせます。胸骨圧迫を行う人は傷病者の横に両膝を立てて座りましょう。圧迫の手順は以下の通りです。
- 胸の真ん中に片手の付け根を置き、もう片方の手を重ねる
- ひじを伸ばし、体重を使って垂直に押す
(浅くても胸が5センチは沈むように圧迫し、元の位置に戻す) - 1分間に100回行うくらいのテンポで30回したら、人工呼吸を2回する、を繰り返す
※人工呼吸をしない場合は胸骨圧迫を繰り返す
人工呼吸の手順
人工呼吸は呼吸がない場合に行いますが、感染症のリスクなどがある場合は無理にする必要はありません。また、できるだけ早く行い、胸骨圧迫に時間をかけるようにしましょう。人工呼吸の手順は以下の通りです。
- 下あごに片手の指、額にもう片方の手のひらを当ててあごを上げるようにして気道を確保する
- 大きく口を開け、傷病者の口を覆うようにして息を吹き込む
(1秒かけて、胸がふくらむようにゆっくり息を吹き込む) - 口を離し、傷病者の息を確認する
- もう1度行い、胸骨圧迫に移る
AEDの使い方
胸骨圧迫や人工呼吸でも心肺が回復しない場合、近くにAEDがあればそれも使用しましょう。AEDが到着してからの手順は以下の通りです。
- 傷病者の近くに置き、電源を入れる
- 電極パッドに表示されたイラストの通りに、パッドを貼る※
- 「体から離れてください」と音声ガイドが流れたら傷病者から離れる
- 音声ガイドに従い、電気ショックを行う
- 音声ガイドに沿って電気ショック、もしくは胸骨圧迫や人工呼吸を繰り返す
※電極パッドにはイラストのように、どの位置に貼るかがわかりやすく示されています。絵の通りの場所に貼ることで電気ショックが正しく行われます。
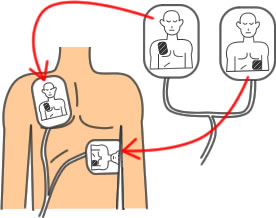
応急処置を本格的に学びたいと思ったら
この記事では応急処置(救急救命)の方法を解説していますが、文章だけでは分かりづらい、実際にやってみないとわからないということも多くあるでしょう。
最後に、応急処置をより詳しく学びたい方におすすめの講習やサイトをご紹介します。
救命講習の受講
胸骨圧迫や人工呼吸、AEDの使用方法を実践しながら学びたいという方は、救命講習を受講しましょう。救命講習は消防署や、全国の日本赤十字社などで実施しています。
自治体や日本赤十字社に問い合わせをし、受講の申し込みをしてください。ちなみに、救命講習の受講をすると修了証がもらえます。
座学や人形を使っての実技で、しっかりと知識や技術を身に付けましょう。
オンラインで学ぶなら
消防庁のサイトでは、一般市民向けの応急手当WEB講習を実施しています。
WEB講習は、動画によるわかりやすい講習となっており、最後には修了テストで知識の確認も可能です。
WEB講習は無料ですので、スキマ時間に正しい知識を身に着けたいという方はぜひ視聴してみてください。
まとめ
応急処置は傷病者の症状を悪化させないために必要な手当てです。正しい知識と技術を身に着けること、傷病者を助けたいという気持ちと勇気を持つことが、応急処置をする際に大切なことだといえます。
応急処置は無料で、さまざまな場所で学ぶことができます。ボランティア団体が講習を行っている場合もありますので、ぜひ参加し、正しい方法を知りましょう。