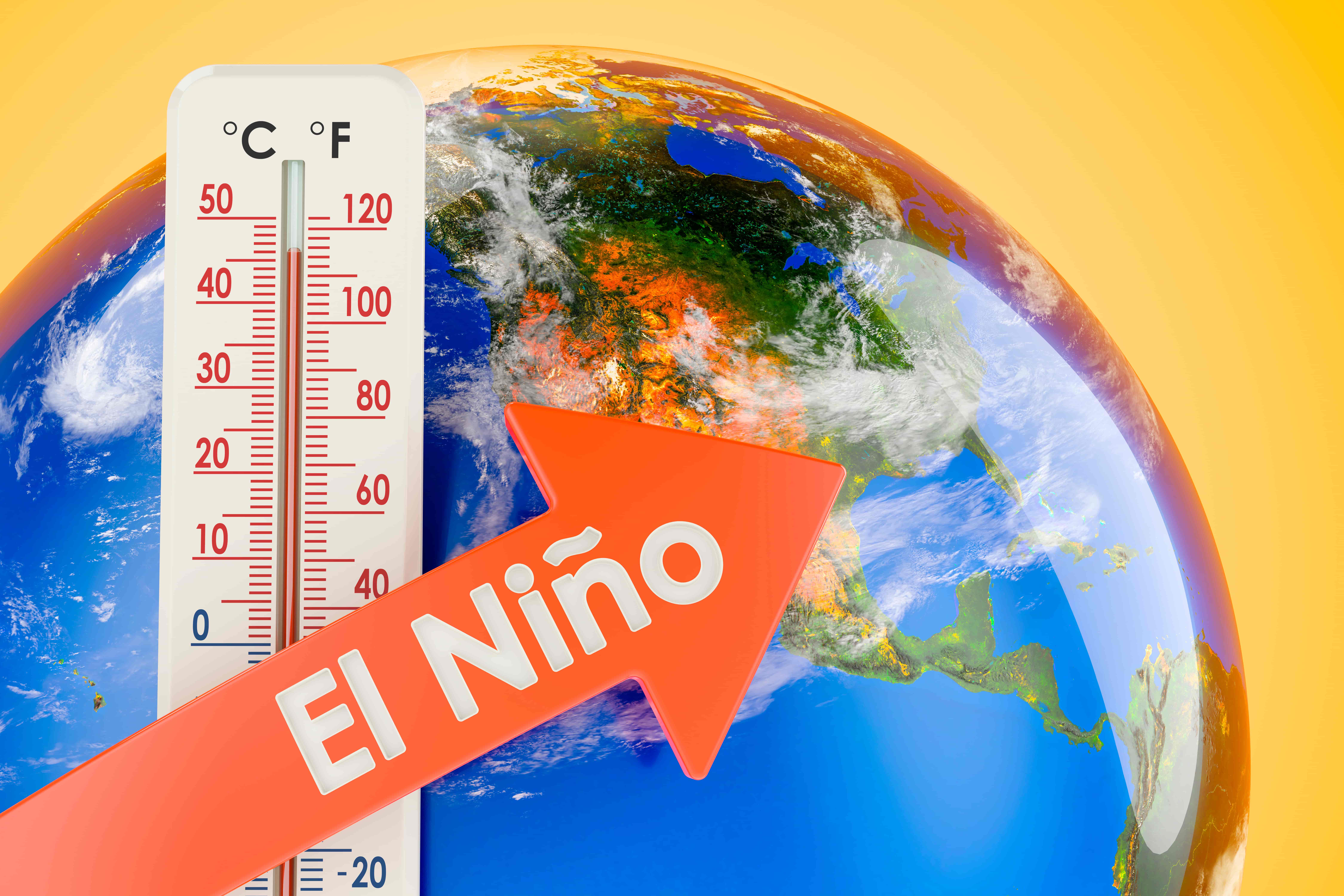本サイトはプロモーションが含まれています。
火砕流や火山の形は「マグマ(溶岩)の温度や粘り気」とどう関係している?
火山が噴火すると、地中の「マグマ」が地上に噴き出します(これが「溶岩」です)。
その結果、火砕流や溶岩流が発生、そして火山の形ができあがります。
今回は、前回(火砕流の速度)、前々回(火砕流と溶岩流の違い)の記事をおさらいをしながら、「マグマ(溶岩)の温度と性質(粘性)」そして「火山の形」との関係についてお伝えします。
火山の噴火にともなって生じる現象を、できるだけわかりやすく解説します。ぜひご覧ください。
火砕流の温度は溶岩流よりも低い
はじめに、火砕流(かさいりゅう)と溶岩流の温度についてみてみましょう。
どちらも「噴火によって噴き出されたマグマが元になって発生する現象」ですが、その温度には違いがあるのです。
火砕流の温度は700~900℃
火砕流とは、地中から噴き出された火山ガスと火山灰などがまざったものが、一気に流れ下る現象のことです。
この噴き出たもの(火山噴出物)の元になっているのは、地中にある「マグマ」です。噴き出したマグマ(溶岩)の温度は「700~900℃」であり、これは、噴き出されるマグマのなかでは低いといいます。
では、溶岩流の温度はどうでしょう。
溶岩流の温度は1000~1200℃
溶岩流とは、火口から噴き出した溶岩(地中のマグマが噴火で地上にあらわれたもの)が、下方へ川のように流れ下っている現象です。
この噴き出したマグマ(溶岩)の温度は「1000~1200℃」と高温であり、溶岩流の特徴の1つとされています。
このように、マグマ(溶岩)の温度の違いによって、火砕流または溶岩流という異なる現象がもたらされるのです。
マグマの温度の違いは“粘り気”とも関係する
では次に、火砕流と溶岩流の元になる「マグマ(溶岩)の温度と粘性」の関係についてみてみましょう。
火砕流の元になるマグマは、粘り気が強い
火砕流の発生には「溶岩ドーム」が関係しています。
溶岩ドームとは、地中から噴き出したマグマ(溶岩)が火口付近で固まったもので、その形がドーム型(半球状)なのです。
火砕流の元になる「700~900℃」という温度は噴き出されるマグマ(溶岩)のなかでは低く、その粘り気は強いとされています。
そのため、噴火の勢いがあっても下方には流れず火口付近に溜まり、盛り上がった状態で固まるのです。
この溶岩ドームと火砕流の発生をまとめると、次のようになります。
◆火砕流が発生するメカニズム
粘り気の強いマグマが噴火によって噴き出す
↓
火口付近に溶岩ドームを形成
↓
噴火活動がつづき、次第に溶岩ドームが崩れだす
↓
吹き出した高温の火山ガスと多量の火砕物が、一気に流れ下っていく(火砕流の発生)
なお、火砕流と溶岩ドームのしくみは、NHK for school「溶岩ドームと火砕流のしくみー中学」(3分)でも確認できるので、ご覧ください。
溶岩流の元になるマグマは、粘り気が弱い
では、溶岩流ではどうでしょう。
溶岩流のもとになるマグマ(溶岩)は「1000~1200℃」と高温で、粘り気が弱い性質となります。
この溶岩の性質は「玄武岩質(げんぶがんしつ)」とよばれ、地球の表面(地殻)を構成するもっとも基本的な岩石だとされています。
ここまで、マグマ(溶岩)の温度と性質(粘性)のちがいから、火砕流と溶岩流についてみてきました。ここで一度まとめてみましょう。
まとめ➀ マグマ(溶岩)の温度・性質と「火砕流(溶岩流)」の関係
「マグマ(溶岩)の温度・粘り気(粘性)・噴火したときの現象」をまとめると、次のようになります。
粘り気(粘性)をイメージしやすいよう、“お餅”を例にとりあげます。
| マグマ(溶岩)の温度 | 粘り気(粘性)お餅で例えると? | 噴火したときの現象 |
|---|---|---|
| 低い(700~900℃) | 強い(お餅では・・少し冷めて固くなりかけている状態) | 溶岩ドームをつくり、火砕流の発生につながる。 |
| 高い(1000~1200℃) | 弱い(お餅では・・沸騰したお湯のなかでドロドロになっている状態) | 溶岩流となって流れ下る |
このように、マグマ(溶岩)の温度・粘り気(粘)の違いは、噴火でもたらされる現象に影響するのです。
そしてこの違いは、火山の形にも関わってきます。
火山の形はマグマの温度によって異なる
では次に、マグマ(溶岩)の温度・粘性と「火山の形」の違いについてみてみましょう。
火山の形には「溶岩ドーム状」「楯状(たてじょう)火山」「成層火山」があります。順にみていきましょう。
温度は低く・粘り気が強い「溶岩ドーム状」
火砕流の発生メカニズムそして先ほどの表でも示したように、温度が低く粘り気が強いマグマ(溶岩)は噴火によって溶岩ドームをつくります。
溶岩ドームはその名のとおり、球体を半分にしたようなドーム型、別の表現で言い換えると「お椀をひっくり返したような形」の火山になります。
溶岩ドーム状の火山を1つご紹介しましょう。

これは、北海道壮瞥町(そうべつちょう)にある「昭和新山(しょうわしんざん)」です。
昭和新山は、1943年(昭和18年)から1945年(昭和20年)の噴火活動でつくられました。このときの噴火では、平坦な麦畑が約300mも盛り上がり、さらにその上に約100mもの溶岩ドームが形成されたとされています。
盛り上がった形がはっきりとわかりますね。
温度は高く・粘り気が弱い「楯状火山」
一方、温度が高く(1000~1200℃)粘り気が弱いマグマ(溶岩)によって溶岩流が発生、そして冷え固まると「なだらかな丘のような形の火山」をつくります。
これは「楯状火山(たてじょうかざん)」とよばれており、主な岩石は「玄武岩(げんぶがん)」です。
たとえば、世界でもっとも活発な火山といわれるハワイ島の「キラウエア火山」は、典型的な楯状火山といわれています。
キラウエア火山は2018年(平成30年)5月に大きな噴火があり、その後も2021年9月そして2023月1月にも噴火がおきています。
マグマの温度・性質は中間「成層火山」
ここまで、マグマ(溶岩)の温度が低い火山、そして高い火山にわけてみてきましたが、火山の形にはもう1つあります。
それは「成層火山」とよばれ、富士山がこの形になります。
マグマ(溶岩)の温度・粘り気ともに中間に位置づけられています。
まとめ➁ マグマ(溶岩)の温度・性質と「火山の形」の関係
ここで再び、先ほどの表をつかって、マグマの温度・粘性のちがいによる「火山の形」をまとめてみましょう。
| マグマ(溶岩)の温度 | 粘り気(粘性)お餅で例えると? | 火山の形 |
|---|---|---|
| 低い(700~900℃) | 強い(お餅では・・少し冷めて固くなりかけている状態) | 溶岩ドーム状(昭和新山) |
| 中間(950~1200℃) | 中間 | 成層火山(富士山) |
| 高い(1000~1200℃) | 弱い(お餅では・・沸騰したお湯のなかでドロドロになっている状態) | 楯山火山(キラウエア火山) |
わたしたちが何気なく見ている山の形は、マグマ(溶岩)の温度や性質によって変わってくるのですね。
火山(噴火)という災害を知る
今回は、マグマ(溶岩)の温度と性質(粘性)をとおして、「噴火によってもたらされる現象(火砕流・溶岩流)」と「火山の形」についてみてきました。
火山やマグマ(溶岩)については小中学校で習いますが、火山が近くにないと、それを身近に感じるのは難しいことがあるかもしれません。
ですが、火山の噴火は台風や地震とおなじ「自然災害」です。それによって、わたしたちの生活そして命に大きな影響をもたらすことは、火山の噴火でも同じです。
今回の記事をとおして、噴火という「災害」そして、「災害がもたらすこと」を考えるキッカケとなれば幸いです。
【参考文献(参考サイト)】
小学館:小学館の図鑑NEO『地球』
コトバンク:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「昭和新山」
在ホノルル日本国総領事館「キラウエア火山噴火に関する注意喚起」
YAHOO!JAPANニュース「ハワイのキラウエア火山が噴火、警戒レベル引き上げ」
(以上)